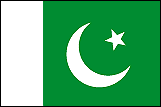
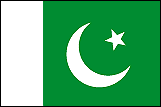
2008年6月17日(火)
『パオ・キャラバンサライ』
JR東中野駅 西口 徒歩数分
http://www.paoco.jp/caravan/index.html
お酒が、日本酒だったのよね、、、。
なぜ、ここで日本酒??
ちょっと納得いかなかったり、、、。(じゃみーら)
≪天(てん)の河 地の河≫
少年は、隣近所もない深い山の中に祖父と二人で山羊を追い、急な斜面を段々に切り開いた狭い畑地を耕して暮らしていた。
少年が生まれたのは、もっと南の人々やロバが行き交うにぎやかな都会の町だった。
少年の母は胸を患い、5歳の息子を残してこの世を去ってしまった。
父親は妻の葬儀が済むと、幼い子供を人里離れた山の中で仙人のような暮らしをしている彼の父親にあずけて、稼ぎのよい石油のとれる国に出稼ぎに行ってしまった。
10歳の少年にとって、共に暮らしている祖父は、父であり母であり、10頭の山羊は兄弟でもあり、仲のよい友達でもある。
実の母の記憶はあまりにも薄く、美しく優しい女性(ひと)だったというような漠然とした記憶しかない。
でも、ひそかに母と一緒に写っているセピア色の写真を宝箱の一番下に入れて大事にしまってある。
褐色の肌に大きな丸い目をした優しそうな女性の膝に同じ目をした小さな男の子がちょこんと座っている。
たびたび出したり仕舞ったりしているので、写真はすっかり汚れてしまっている。
4本の足がついていて、ふたの部分に象眼細工のほどこされた美しい木の箱は、彼の父が遠い国から友人の手を通して贈ってくれたものだ。
少年はその中に、山羊の抜けた歯や木の実や形のよい石などと一緒に母の写真を大切に仕舞った。
時々、空が真っ青に晴れ上がって気持ちのよい日など、山羊の放牧に出るとき、宝物を入れた小箱を小脇に抱えて外に出た。
大きな樹の下に座って、そっと小箱を開ける。
早く一番下の写真を取り出したい気持ちを抑えて目を上げる。
向かい側の濃い緑色の樹の茂った山のふちに帯のように細い道が走っている。
さらに視線を上げると、山と山の間の奥の方に万年雪を抱いた山がそびえている。
頂上は雲の中に隠れている。
ずっと見ていると、時折雲が風に流されて、その鋭い頂を現す瞬間がある。
同じ山が時間や天候によってまったく異なった姿に見えることを少年は知っている。
夜明けの最初の一条が暗闇の世界に光を投げかけて、徐々にそれが広がっていくとき、山は低い位置からライトアップされて、自然の生みなす崇高な光と影のショーを演ずる。
日中、日が高く昇ると、山はもはや光の陰影を失い、平面的に見える。
夕方、西の空に日が傾き始めると、再び山々は生き生きと蘇る。
雪の上に光のあたった部分は薄桃色に色づく。
少年はそのピーチ色に染まった雪山を見ながら、昔会った少女の上気した頬にそっくりだと思った。
それはまだ優しい母がいて、南のにぎやかな町に住んでいた頃のことだった。
白い半袖のワンピースを着た金色の髪の少女が、風に飛ばされた麦藁帽子を追いかけて走ってきた。
少年が帽子を拾って目を上げると、色白の陶器のような肌が走ってきたせいで薄くピンクに染まったお人形さんのように愛らしい顔の青い瞳と目があった。
少女は笑顔で「サンキュー」と言うと、帽子を渡してくれるように右手を差し出した。
笑うとえくぼができた。
少年は恥ずかしかったので、怒ったような顔をして無言で、ただ帽子をもった右手を前に差し出した。
少年は山に来てから、雪山が夕焼けに色づくのを見るたびに名前も知らないあの少女のことを思い出した。
いつのまにか眠ってしまった少年は、山羊に顔をなめられて目を覚ました。
辺りはすっかり薄暗くなっていて、冷たい風が吹いている。
くしゃみを一つして立ち上がると、慌てて山羊を集めて家路についた。
「ただいま」
暗い家の中は、何の物音もしない。
「おじいちゃん!」
声をかけながら部屋の中に入る。
少年の祖父が下を向いて絨毯の上に座っている。
チャイ(紅茶)のコップが横に倒れて、アラベスク模様の絨毯の上に黒い染みをつくっている。
「ねえ、おじいちゃん」
もう一度声をかけながら肩に手を触れると、そのまま斜め前に倒れてしまった。
まるで眠っているような安らかな死に顔だった。
少年は泣きながら外に出て、夜空を見上げた。
山の澄み渡った空に満点の星が輝いている。
天にも河が流れていて、天にも人や動物がいることを教えてくれたのも祖父だった。
天(てん)の河が雪山の向こうに流れこんで、それが地の河につながっているのだと。
死んだ人は地の河をさかのぼって天の河にたどりつくと・・・
そして、心の中で呼べば、いつでも会うことができるのだと・・・
しかし、今は少年は知っていた。
二度と祖父の自分を呼ぶ声を聞けないと。
二度とたくましい胸に抱きしめて、ふしくれだった手で背中を撫でてくれないと。
もう髯もじゃの頬で、頬ずりをしてくれないと・・・
涙で潤んだ瞳に天の河はぼやけてゆがんでしまった。
眼下では、地の河が静かな水音をたてながら夜の闇へと流れこんでいた。 (みやちゃん)